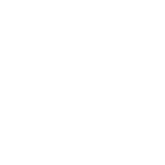近畿大学附属広島高等学校福山校の生徒を対象としたカーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。
将来的な、カーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う人材育成に向け、近畿大学附属広島高等学校福山校において、高校生21名を対象に、カーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を3週に渡って実施しました。今回は第1回と第3回の内容を中心にご紹介します。
●開催日 <第1回>2025年10月9日(木)12:00~12:50
●開催場所 近畿大学附属広島高等学校 福山校
●各回の内容
・第1回(10/9実施) :カーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業
・第2回(10/16実施):講演内容を踏まえた議論とプレゼンテーションに向けたプランニング
・第3回(10/23実施):探究成果プレゼンテーション
■授業風景<第1回>
近畿大学附属広島高等学校福山校では、2024年4月から、福山市内にある約100万本のばらの剪定枝を再生可能エネルギー「ばらのバイオコークス」として製造・活用する探究活動を進めています。そこで、初回の授業では、バイオコークスの開発や炭化装置の製造を手がける株式会社ZEエナジーにご協力いただき、バイオコークスをテーマに、カーボンリサイクルやカーボンニュートラルに関する基礎知識や最新の取組について学びました。
はじめに、広島県から「二酸化炭素」に関する講義を行いました。二酸化炭素が地球上に過剰に堆積してしまっている現状に対し、カーボンニュートラルの実現を踏まえると、バイオコークスの利用にあたっては、材料の採集から輸送、製造、使用に至るまでの流れ全体を考慮に入れ、二酸化炭素の排出を考える必要があることを伝えました。
また、二酸化炭素は生物の源であり、炭素循環によって生態系が維持されていることや、地球の温度を保つのに不可欠な存在であることなどの重要な側面に触れ、その理解を深めました。そのうえで、二酸化炭素の排出を減らす取組だけでなく、二酸化炭素を分離回収し、利用することも同時に行うことの重要性や、実際に広島県内で取り組まれているカーボンリサイクルの研究事例などを学びました。
生徒からは、「カーボンニュートラルを達成するために、燃料を削減したり、木を植えたりする以外にも、二酸化炭素を資源として利用したり、地中に埋めたりするなどの活用方法もあると新しく学んだ」「単に二酸化炭素を減らすだけではなく、二酸化炭素を減らす過程そのものでも環境への配慮が必要であること、さらに減らした後のことまで考えなければならないという視点に気づき、とても勉強になった」との声がありました。
続いて、株式会社ZEエナジーより、バイオマスコークスやバイオ炭の利用について、基礎知識から現在進めている具体的なプロジェクトに至るまで解説いただきました。炭化させたバイオマスを、コークスだけではなく、農地にすき込んで肥料として使用するなどの様々な活用方法について、また、コストや環境負荷を抑えるために、地産地消でバイオマスコークスを製造することの重要性について紹介いただきました。
また、生徒が製作したバイオマスコークスのサンプルを前に、自社製品との比較や、キュポラ等で必要とされている規格を踏まえて、生徒に対して、品質の向上や炭化方法に関する研究のアドバイスを送りました。
講演の後の質疑応答の時間では、生徒は積極的に手を挙げて、率直な感想や疑問を投げかけ、それに対して丁寧に回答いただきました。また、授業が終わった後も、生徒は自分たちの研究課題や疑問点について熱心に質問し、知識を補強したり活発に意見を交換したりしていました。
生徒からは、「工業におけるコークスの活用方法についてあまり知らなかったため、興味が湧いた」「製造方法を工夫することで、探究活動で使用していたものとは違って、より熱量が高く崩れにくいバイオマスコークスを作ることができると知り、試作してみたいと思った」などの感想がありました。
■授業風景<第3回>
第1回の講義で学んだ内容を取り入れて、第2回の授業では、現在の研究内容のアップデートや、新しく見えてきた研究課題と今後の取組について議論しました。それを受けて、第3回はオンラインにて探究成果プレゼンテーションを実施し、バラのバイオマスコークスを使って、ミニSLを走らせる実験を行っているチームや、団子を焼いて地域のイベントで販売しているチームなど、計4チームが発表を行いました。
バイオマスコークスを地域産業の一つとして取り入れ、経済の活性化を図る提案や、地域で排出されたものを地域でバイオマスコークスとして再利用し、地域資源を生かしたエネルギーづくりに取り組みたいとした提案など、講演の中でも示した、地産地消の大切さを早速プレゼンテーションに取り入れているチームが多く見られました。
それぞれのプレゼンテーションに対しては、広島県と株式会社ZEエナジーより、「材料別にバイオマスコークスの用途を変更してはどうか」「バイオマスコークス以外にも様々な環境に関する取組があるので、多角的な視点をもって、課題を捉えてみると新しい発見を得られるのでは」などといった、講評や具体的なアドバイスを送りました。
■まとめ
生徒に対し、カーボンニュートラルの実現に向けて、カーボンリサイクル技術が注目されていることや、その重要性を伝える貴重な機会となりました。また、今回の授業を通してバイオマスコークスの探究活動に関する新しい知識を得た生徒が多く、次世代を担う高校生の取組を大きく後押しすることができました。
生徒が、二酸化炭素の排出や、その利用価値について深く考察していた姿や、前向きな意見・感想が寄せられたことから、次世代教育の重要性を改めて実感いたしました。こうした、将来的なカーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う次世代との交流にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ事務局までご相談ください!
<協力>
株式会社ZEエナジー