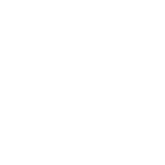広島県瀬戸内高等学校の生徒を対象としたカーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。
将来的な、カーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う人材育成に向け、広島県瀬戸内高等学校において、希望者15名を対象に、カーボン・サーキュラー・エコノミーを学ぶ特別授業を開催しました。
●開催日 2025年9月24日(水)15:40~16:40
●開催場所 広島県瀬戸内高等学校
■授業風景
テーマを「二酸化炭素×微細藻類」と題し、地球温暖化と二酸化炭素の関係性や、カーボンニュートラルの実現に向けて、その一つの対策として注目されているカーボンリサイクルや微細藻類の可能性について学びました。
はじめに、広島県から「二酸化炭素」に関する講義を行いました。現在、地球温暖化がどの程度進行しているのか、グラフや表を用いて説明した後、生徒たちは、二酸化炭素が地球上に過剰に堆積してしまっている現状に対し、二酸化炭素の排出量と森林等による吸収量のバランスを均衡にするカーボンニュートラルを目指す必要があることを学びました。
また、参加した生徒は、環境に悪いと認識しがちな二酸化炭素が、地球の温度や多様な生態系の維持に不可欠な存在であるという多角的な視点に触れ、その理解を深めました。さらに、県内で進められているカーボンリサイクルへの取り組み事例も紹介し、地域における具体的な活動を知る機会となりました。
続いて、株式会社アルガルバイオより、同社の事業概要と起業までの経緯、そして主力技術である「微細藻類」の驚くべき可能性について、具体的な事例を交えながら解説いただきました。特に、微細藻類が二酸化炭素を効率的に吸収し、食品や燃料、化粧品など多様な製品に利用される最先端のバイオビジネスのプロジェクトの事例は、生徒の大きな関心を集めました。
また、講演の後の質疑応答の時間では、たくさんの色素を持つ微細藻類に興味を持った生徒から「ピンク色の藻類は作れないの?」や、「一番好きな藻類は何?」「藻類が木よりもたくさん二酸化炭素を吸ってくれると聞いたが本当なの?」といった高校生らしい素朴な疑問がたくさん寄せられ、それに対して、研究者の視点から、藻類の造形美や未知なる藻類を発見することへの好奇心、陸上植物よりも高効率で二酸化炭素を固定することができる藻類のポテンシャルの高さなどのお話をいただき、活発に意見を交換していました。
特別授業を通して、生徒からは「講演前は二酸化炭素を減らすことばかり考えていたが、吸収することや利用することもできると知って、減らすことばかり考えていたらダメだと分かった」「今までは二酸化炭素は悪者というイメージがあったが、それが生活上で役に立っていることを知り、いいやつだなと思うようになった」「授業を通して、これから地球を守っていくために藻類が活躍すると知って、藻類に関わる仕事も楽しそうだなと思った」との感想がありました。
■まとめ
生徒に対し、カーボンニュートラルの実現に向けた手段の一つにカーボンリサイクルという技術があることや、その重要性を伝える貴重な機会となりました。二酸化炭素の排出や、その利用価値について深く考察していた姿や、前向きな意見・感想が寄せられたことから、次世代教育の重要性を改めて実感いたしました。こうした、将来的なカーボンリサイクル関連技術の研究・開発等を担う次世代との交流にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ事務局までご相談ください!
<協力>
・株式会社アルガルバイオ